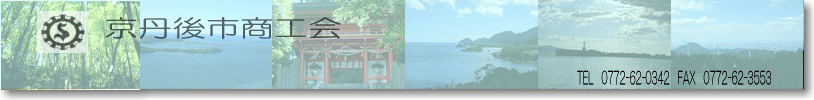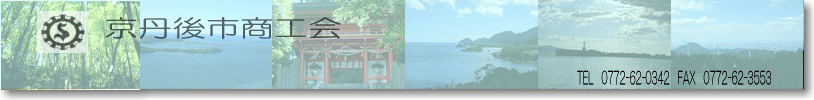| イ. |
青色申告の主なメリット |
|
| 項目 |
青色申告者 |
白色申告者 |
| 専従者給与 |
適正な金額の範囲内は全額必要経費算入 |
専従者1人当り最高50万円(配偶者は最高86万円) |
| 青色申告特別控除 |
所得計算上、65万円、10万円の特別控除額を控除出来る。 |
適用なし |
| 現金主義 |
現金主義による所得計算:
前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が300万円以下の人 |
適用なし |
| 純損失の繰越控除 |
純損失について、翌年以降3年間繰越控除 |
一定の損失に限り繰越控除可能 |
| 純損失の繰戻還付 |
純損失について、前年分の税額から還付 |
適用なし |
| 減価償却 |
中小企業者の少額減価償却資産の一括経費算入 |
適用なし |
| 更正の制限 |
帳簿調査に基づかない更正は不可 |
帳簿調査に基づかない更正が可能 |
| 更正の理由附記 |
更正通知書にその更正理由が附記される |
更正理由の附記は不要 |
| 推計課税 |
推計課税による更正・決定は不可 |
推計課税による更正・決定が可能 |
|
|
 専従者給与 専従者給与 |
|
青色申告者が生計を一にする配偶者その他の親族で専らその事業に従事するものに対して支払った給与は、所得の計算上、全額必要経費に算入することが出来ます。
この規定の適用を受ける場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」に所定の事項を記載し、所轄税務署長に提出しなければなりません。
|
| 事業専従者とは… |
|
|
次のいずれにも該当する人をいいます。 |
 |
納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であること |
 |
その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること |
 |
事業に従事可能な期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事していること |
|
|
|
次の方は事業専従者には該当しません。 |

|
学生、他に職業がある人(但し、事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合を除く。) |
 |
老衰その他心身の障害によって事業に従事する能力が著しく阻害されている人 |
|
| 青色事業専従者給与に関する届出書 |
|
|
提出期限: 適用を受けようとする年の3月15日まで |
|
届出事項: 事業専従者の氏名・続柄・年齢
職業の内容、給与の金額・支給時期
他の使用人に対して支払う給与の金額、支給の方法、形態
昇給の基準 など |
|
※届出の給与の金額等を変更する場合、新たに専従者が加わった場合には、遅滞なく、変更届出書を提出しなければなりません。 |
|
| 青色事業専従者給与の適正額の判定基準等 |
|
 |
労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度 |
 |
他の使用人が受ける給与の状況 |
 |
同種同規模事業に従事する者の給与の状況 |
 |
その事業の種類・規模及びその収益状況 など |
|
|
|
|
 青色申告特別控除 青色申告特別控除 |
|
事業を営む方で、これらの所得金額にかかる取引を「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」に従って記録している方については、一定の要件の下で、その年分の事業所得の計算上、青色申告特別控除として、最高65万円(平成16年分以前は最高55万円)を控除することができます。
上記以外の方については、青色申告特別控除として、最高10万円を控除することができます。 |
|
|
|
 純損失の繰越控除 純損失の繰越控除 |
|
青色申告書を提出している年において生じた純損失については、他の所得と損益通算後3年間の繰越控除をする事が出来ます。
注意:不動産所得の必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算、繰越控除出来ません。
損失が生じた年の青色申告書は期限内に提出し、その後の年においては引き続き確定申告書を提出しなければなりません。
※純損失の金額
事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得(株式等、土地等・建物等の譲渡を除く。)の金額の計算上生じた損失の金額について、損益通算によってもなお引ききれなかった損失の金額をいいます。 |
|
|
|
 純損失の繰戻還付 純損失の繰戻還付 |
|
青色申告書を提出している年において生じた純損失については、その純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算し、その差額の税額の還付を請求することができます。
ただし、前年分についても青色申告書を提出している場合に限ります。 |
|
|
|
 少額減価償却資産の即時償却 少額減価償却資産の即時償却 |
|
| ① |
青色申告者が一定の期間内に取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額を必要経費に算入する事ができます。 |
| ② |
上記①の即時償却ができるのは、取得価額の合計額が、1年間(1月1日~12月31日)で300万円(年の中途に開業した方の場合は、月数按分)までの資産に限られます。300万円を超える部分は、通常の減価償却をすることになります。
対象資産:平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得した資産
※資産の種類は問いません。 |
|
金額別:取得価額30万円未満の減価償却資産の処理方法 |
|
| |
法定償却 |
3年間の一括償却 |
全額経費算入 |
| 10万円未満 |
○ |
○ |
○ |
10万円以上
20万円未満 |
○ |
○ |
○
(青色のみ) |
20万円以上
30万円未満 |
○ |
× |
○
(青色のみ) |
|
|
|
|
|
 更正・決定 更正・決定 |
|
・更正とは
納税者の提出した申告書につき、その課税標準等又は税額等が税務署が調査したところと異なる場合に、税務署長がその税額等を増額又は減額させる処分をいいます。
・決定とは
申告書を提出すべき人がその申告書を提出しなかった場合に、調査等により税務署長がその納付すべき税額を確定させる処分をいいます。 |
|
(除斥期間)
| |
除斥期間 |
| 増額更正 |
3年 |
| 減額更正 |
5年 |
| 決定(無申告) |
5年 |
偽りその他不正行為(脱税)
の場合の更正・決定 |
7年 |
|
| ロ. |
青色申告の承認 |
|
【青色申告の要件】
・帳簿書類の備え付け・記録・保存
・税務署長に「青色申告の承認の申請書」を提出し、予め承認を受けること
【青色申告の承認申請書の提出】
○原則
青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに提出
○新規開業
業務を開始した日から2ヶ月以内に提出
○相続の場合(相続前に業務を行っている者を除く。)
・1/1~8/31の間に死亡:死亡の日から4ヶ月以内に提出
・9/1~10/31までの間に死亡:その年12/31までに提出
・11/1~12/31までの間に死亡:翌年2/15までに提出 |
| ハ. |
帳簿書類と保存期間 |
|
【備え付けるべき帳簿】
| 帳簿の種類 |
複式簿記 |
簡易簿記 |
現金主義 |
| 現金出納帳 |
○ |
○ |
○ |
| 預金出納帳 |
○ |
|
|
| 売掛帳(売上帳) |
○ |
○ |
現金収支による管理 |
| 買掛帳(仕入帳) |
○ |
○ |
現金収支による管理 |
| 経費帳 |
○ |
○ |
現金収支による管理 |
| 固定資産台帳 |
○ |
○ |
|
| 仕訳帳 |
○ |
|
|
| 総勘定元帳 |
○ |
|
|
|
|
【参考】白色申告者の記帳義務
その年の前々年又は前年の不動産所得、事業所得又は山林所得の合計額が300万円を超える人は、一定の帳簿を備えつけて簡易な方法により取引を記録し、かつ、その帳簿や関係書類を保存しなければなりません。 |
|
【帳簿の保存期間】
| 書類 |
具体例 |
青色申告者 |
白色申告者 |
| 帳簿 |
現金出納帳、仕訳帳、
総勘定元帳など |
7年 |
7年 |
| 決算書類 |
貸借対照表、損益計算書、
収支計算書など |
7年 |
7年 |
現金預金取引等
関係書類 |
領収書、請求書、
預金通帳など |
7年 |
5年 |
| その他 |
証ひょう書類 納品書、請求書控、
契約書など |
5年 |
5年 |
|